「論述試験の問題を解いてみたけれど、自分の解答が本当に正しいか分からない…」
「解答例を見ても、なぜその答えになるのか、その意図が理解できない…」
国家資格キャリアコンサルタントの論述試験は、明確な「これだ!」という一つの答えがあるわけではなく、その考え方は人それぞれです。
この記事は、キャリアコンサルティング協議会(CC協議会)の試験問題について、あくまで私個人の思考プロセスをまとめたものです。
この記事が、あなたの解答の「正解」ではなく、合格という結果を掴むための一つの有効な視点として学習の助けになること願って作成しました。
そのため、回答については意識的に少し多めの文字数で作成しています。
私自身が実技試験でオールA評価を獲得した経験から、第29回論述試験の設問に対し、解答例だけでなく、対策ポイントを徹底的に解説します。

【事例記録】の概要
今回の事例は、定年退職後1年が経過した61歳女性、Zさんです。
仕事中心だった生活から一変し、現在は高齢の両親の手伝いをしながら、漠然とした「充実感のなさ」を感じています。
仕事は大変だったもののやりがいや充実感があった過去と比べ、新しい働き方や生き方を模索している状況です。
設問1: 相談者がこの面談で相談したいことは何か
【設問の意図】
この設問は、相談者の言葉を表面的なものとして捉えるだけでなく、その背景にある「本質的な相談内容」を正確に把握できているかを確認するものです。
単に「仕事を探したい」と書くのではなく、Zさんが抱える葛藤や、本当に求めているものを読み解く力が問われています。
【解答例】
定年退職後の生活に充足感が得られず、再び働くことに興味はあるものの、高齢の両親のこともあり、仕事と両立できるか不安を感じている。
そのような現状で、今後どのようにキャリアと生活のバランスを取っていくべきか、方向性を見出したいという相談である。
【解答のポイント】
設問2: 下線部Bのキャリアコンサルタントの応答の意図
【設問の意図】
この設問は、事例記録中のキャリアコンサルタントの応答に対し、その「応答の意図」を論理的に説明できるか、つまりカウンセリング技法の目的を理解しているかを問うものです。
この応答は、相談者の言葉をそのまま繰り返す「繰り返し・おうむ返し」の技法です。
【解答例】
相談者の「両親の身の回りの手伝いをしなければならないけれど、やっぱり少し働いた方がいいのかな…」という発言を受け、両親の支援と仕事の両立について、相談者自身の言葉を繰り返すことで、その考えを明確化・言語化することを促し、相談内容の焦点を絞る意図があったと考える。
【解答のポイント】
設問3: あなたが考える相談者の問題とその根拠
【設問の意図】
論述試験の核となる、相談者の抱える「真の問題」を見立てる力を問う設問です。
表面的な悩み(仕事探し)ではなく、その背景にある心理的な問題や葛藤を特定し、その根拠を事例記録中の相談者の具体的な言動から見つけ出す必要があります。
【解答例】
① 問題: これまでの仕事中心の価値観から離れられず、定年後の新たなライフキャリアのあり方を構築できていないこと。
② その根拠: 「仕事はずっと忙しくて大変だったので、60歳になったら、もうやらなくてもいいと思った」と話す一方で、定年後の生活に「一日の充実感がない」と感じ、「仕事は大変だったけれど、やりがいがあって毎日が充実していた」と過去を振り返っている点。
また、仕事と両親の世話の両立を「どちらも中途半端になってしまうかもしれない」と決めつけ、新しい働き方をイメージできていない点から、仕事中心の過去の価値観に縛られていることがうかがえる。
【解答のポイント】
設問4: 今後あなたがこのケースを担当するとしたら、どのような方針でキャリアコンサルティングを進めていくか
【設問の意図】
設問3で特定した「問題」を踏まえ、今後の面談で何を、どのような手順で支援していくかを具体的に記述する設問です。
抽象的な「傾聴します」ではなく、Zさんの抱える問題解決に向けて、具体的なプロセスを示すことが求められます。
【解答例】
まず、相談者のこれまでのキャリアの棚卸しを支援し、仕事で得たやりがいや充実感の源泉を言語化することで、働くことの価値観を明確化する。
その際、在職中の「最後の5年間」の部署異動や人間関係の苦労を乗り越えた経験に焦点を当て、本人が自覚していない強みや職業的価値観を一緒に探求していく。
次に、現在の両親のサポートを含む生活の状況を丁寧に聴き取り、仕事以外の役割においても、やりがいや充実感を見出せるよう支援する。
Zさんが「なんとなく一日が過ぎている」と感じる原因を探り、仕事中心だった過去の価値観から離れ、新しいライフキャリアのあり方を共に検討していく。
その上で、「仕事と両親の世話をどちらも中途半端にしてしまうかもしれない」という不安の根源にある「両立」への固定観念を解きほぐす。
具体的な働き方の選択肢として、フルタイムだけでなく、短時間勤務やボランティア、地域活動など多様な選択肢を提示し、仕事と生活のバランスが取れた「自分らしい」生き方を具体的にイメージできるよう支援する方針で進める。
論述試験で高得点を取るための3つのポイント
最後に、今回の設問内容を乗り越えるために、日頃から意識してほしい3つのポイントをお伝えします。
- 「相談者の言葉」を軽視しない
- 「論理の一貫性」を意識する
- 「あなたの視点」を明確にする
論述試験は練習すれば必ず力がつきます!
今回の解説を参考に、何度も繰り返し練習してみてください!
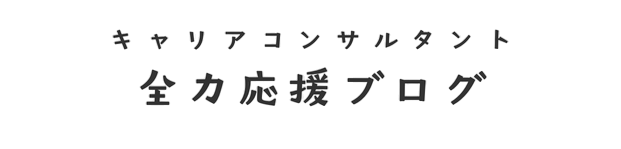




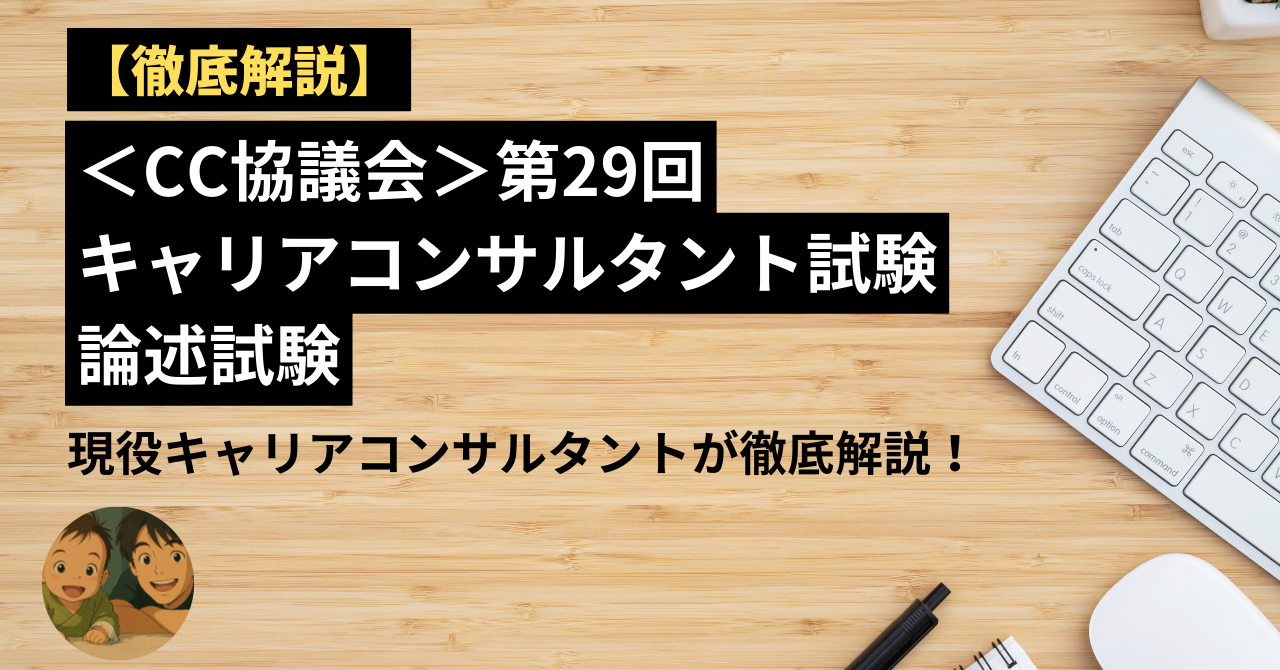
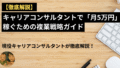
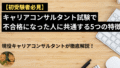
コメント