「ロープレで質問が続かず、沈黙が怖くて焦ってしまう…」
「クライアントの本音にたどり着けず、面談が表面的な話で終わってしまう…」
「質問を考えるばかりに、相手の話を聞き逃してしまうことがある…」
「どうすれば、もっと自然に、効果的な質問ができるようになるんだろう?」
キャリアコンサルタント実技試験のロープレで、「質問力」の壁にぶつかっていませんか?
私自身、養成講座時代から特に質問力で高評価をいただき、一発合格を掴むことができました。
しかし、もちろん最初からスラスラと質問が出てきたわけではありません。
私自身も「質問しなきゃ」というプレッシャーばかりで、頭が真っ白になってしまうこともありましたし、次に何を質問しようかと考えるあまり、クライアントの言葉を聞き逃してしまうという悩みも抱えていました。
そんな私でも、質問の「コツ」と、それを身につけるための「具体的な行動」を知ってからは、面談の流れが劇的に変わりました。
質問が自然に出てくるようになり、クライアントの深い悩みに寄り添えるようになったんです。
この記事では、あなたがなぜ質問に困ってしまうのか、そして質問を考えるあまり聞き逃してしまう原因を明確にし、私が質問をスラスラと引き出し、かつ深く傾聴するために実践していたことを具体的に解説します。
そして、明日からすぐに実践できる「質問力」強化のための方法をお伝えします。

質問の目的と重要性:「聞く」ではなく「引き出す」
キャリアコンサルタントの面談において、質問は単に情報を得るためのツールではありません。
質問の真の目的は、クライアント自身が自身の内面と向き合い、自ら気づきを得て、主体的な行動へと繋がるための「プロセスを促す」ことにあります。
質問が果たす重要な役割
- クライアントの自己理解を深める: 質問を通して、クライアントは自分の考えや感情、価値観を言語化し、客観的に捉え直す機会を得ます。
- 問題の本質を明らかにする: 表面的な訴えの奥にある、真の悩みや未解決の課題を共に探り、明確にします。
- 新たな視点や可能性を広げる: クライアントが固定観念に囚われず、多様な選択肢や解決策に気づくきっかけを提供します。
- 信頼関係(ラポール)の構築: 適切な質問は、クライアントが「理解されている」「寄り添ってもらえている」と感じ、安心感と信頼感を育みます。
- 自律的な意思決定の支援: クライアントが自ら考え、納得して行動に移せるよう、意思決定のプロセスをサポートします。
このように、質問はクライアントの成長と変容を促す面談の最も重要な要素です。
どうして質問が出てこないのか?
多くの受験生が「質問が出てこない」と悩むのはなぜでしょうか?
その背景には、いくつかの共通する理由があります。
自分の状況に当てはまるものがないか、考えてみましょう。
当てはまるものはありましたか?
これらの理由を理解することで、あなたが質問に困ってしまう根本的な原因が見えてくるはずです。
「質問を考えるばかりに話を聞き逃す」理由とその対処法
質問を考えようとすることでかえって相手の話を聞き逃してしまうのは、多くの人が経験する「あるある」な悩みです。
これは、私たちの脳の仕組みと、面談中の意識の向け方に原因があります。
聞き逃してしまう主な原因
- 次の質問を考えることに意識が奪われるから クライアントの話を聞くインプット作業と、次に発言する質問を考えるアウトプット準備を同時に行おうとするため、どちらか一方に集中力が偏ってしまいます。
特に、次に何を言うべきかというプレッシャーから、質問を組み立てることに意識が向かいすぎ、肝心のクライアントの言葉が「BGM」のようになってしまうことがあります。 - 「間」を埋めなければ、という焦りがあるから 面談中の沈黙や、クライアントが言葉を探している「間」を恐れ、「早く次の質問をしなければ」という焦りから、クライアントの言葉を最後まで聞かずに、質問の準備に入ってしまいます。
- 人間の脳はマルチタスクが苦手だから 根本的に、人間の脳は複数の高度な認知タスクを同時に完璧にこなすようにはできていません。
「聞く」という集中を要するタスクと、「考える」という集中を要するタスクの同時進行は、どちらかのパフォーマンスを低下させること(マルチタスクの限界)が科学的にも示されています。
試験中にできる具体的な対策
質問を考えることと、深く傾聴することを両立させるためには意識的なトレーニングが必要です。
ここでは試験中に再現可能な具体的な対処法に焦点を当てます。
1. 抽象的なワードや不明瞭な点を「掘り下げる質問」でクリアにする
クライアントが漠然とした言葉(例:「なんとなく」「もやもやする」「うまくいかない」)を使ったり、話の展開が不明瞭だと感じたりした場合、それをそのまま放置せず、すぐに掘り下げる質問を投げかけることで、その後の質問の方向性が明確になり、聞き逃しが減ります。
この対処法で意識すること
具体的な質問例
2. 感情ワードを「共感・確認の質問」で深掘りし、間を作る
クライアントが感情を表す言葉(例:「不安」「疲れた」「嬉しい」「悔しい」)を発した時、それを拾い上げて共感し、さらにその感情を深掘りする質問を投げかけましょう。
これにより、クライアントは「聞いてもらえている」と感じ、安心感を得られます。
また、感情の確認は、次に質問を考えるための「間」を生み出すことにも繋がります。
この対処法で意識すること
具体的な質問例
3. 最悪、オープンな「振り返り質問」で切り抜ける
もし、上記のような具体的な掘り下げが難しいと感じた場合や、本当に次に何を質問すれば良いか思いつかない場合は、クライアントがこれまで話した内容全体を「振り返ってもらう」ような、オープンな質問で切り抜けることができます。
この対処法で意識すること
具体的な質問例
これらの具体的な質問テクニックを習得することで、「質問を考えながら聞き逃す」というジレンマを解消し、面談の質を高めることができるでしょう!
質問がスラスラ出てくる人は何をしているのか?
では、質問が自然に出てくる人は一体何を意識し、どのような習慣を持っていたのでしょうか?
私は比較的質問が得意だったので、意識していたことをまとめます。
秘訣1:クライアントの「感情」と「価値観」を捉える
私は、クライアントが話す「事実」だけでなく、「その時どう感じたのか」という感情や、「なぜそう思うのか」という価値観に常に耳を傾けていました。
ここに次の質問のヒントが隠されています。
この質問の型で意識すること
実践例
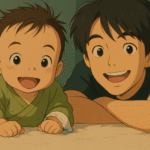
私も最初はクライアントの話す「出来事」ばかりに注目していました。
しかし、「感情」と「価値観」に意識を向けるようになってから、質問が格段にスムーズに出てくるようになりました。
特に「どんなお気持ちでしたか?」は、クライアントの心を開く魔法の質問だと感じています。
秘訣2:「問いかけの引き出し」を増やす思考法
質問が自然に出てくる私は、特定の質問フレーズを暗記しているわけではありませんでした。
私は、一つの情報から複数の「問いかけの視点」を引き出す思考法を身につけていました。
この質問の型で意識すること
実践例
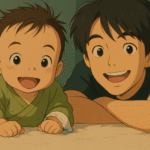
この「思考の引き出し」を意識し始めてから、質問が途切れることがなくなりました。頭の中で常に「他に聞けることはないかな?」と考える癖がついたことで、面談に深みが出ました。
「なぜ?」ではなく「どのように?」や「どういう意味?」に言い換えるだけでも、クライアントの語りは変わってきますよ。
秘訣3:クライアントの「可能性」を信じ、共に探求する姿勢
質問がスラスラ出てくる人には、クライアントが自身の力で答えを見つけられるという「可能性」への深い信頼があります。
私は、クライアントを導くのではなく、共に探求するパートナーとしての姿勢を貫きました。
この質問の型で意識すること
実践例
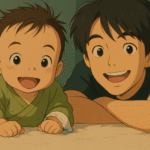
「私が答えを出さなければ」というプレッシャーから解放されてから、質問が格段に楽になりました。
クライアントが自分で答えを見つけた時の表情は、何よりも嬉しいものです。この「信じる姿勢」が、質問をより深いものにしてくれます。
こんなケースにはこんな質問!質問集(5選)
実際にロープレでよくあるケースを想定し、質問に困ったときに役立つ具体的な質問例をご紹介します。
ケース1:クライアントが漠然とした不安を訴えている時 「今の仕事に漠然とした不安があるんです。」
ケース2:クライアントが複数の選択肢で迷っている時 「転職するか、今の会社に残るか、決められなくて…」
ケース3:クライアントが自分の強みや経験を活かせないと感じている時 「自分には特別なスキルもないし、何ができるのか分からなくて…」
ケース4:クライアントが「~べき」「~ねばならない」といった思考に囚われている時 「会社のために、もっと残業するべきだと分かっているんですが…」
ケース5:クライアントが感情的になり、話がまとまらない時 「もう、本当に疲れました…何もかも嫌になります…(涙声)」
明日からできる!質問力を劇的に高める3つの方法
質問力を向上させるために、明日からすぐに実践できる具体的な方法をご紹介します。
方法1:ロールプレイングの「録音・録画」と「徹底的な自己分析」
自分のロープレを録音・録画し、文字起こしをしながら振り返りましょう。
これらの問いを自分に投げかけ、具体的な改善点を見つけます。
方法2:質問の「ストックリスト」と「言い換え練習」
よく使う質問フレーズや、自分が「もっとこう聞きたい」と思う質問をリストアップしましょう。
特に、「なぜ?」を「どのように?」「どう感じた?」などに言い換える練習は、質問の質を上げる上で非常に効果的です。
日々の会話の中でも意識的に練習してみましょう。
ステップ3:「クライアント目線」での質問シミュレーション
ロープレの練習をする際、一度、自分がクライアントになったつもりで、相談内容を深く掘り下げてみましょう。
「自分だったら、どんな質問をしてほしいか?」「どんな質問なら、もっと話せるだろう?」と考えることで、クライアントに寄り添った質問が見えてきます。
記事のまとめ
これらの方法を継続することで、あなたの質問力は確実に向上し、キャリアコンサルタントとしてクライアントの本音を引き出す力が飛躍的に高まります!
しかし、実践的な質問力を身につけるには独学や練習量だけでは限界があります。
正直なところ、私が実技試験でオールAを取れたのは、「小手先のテクニック」ではなく「プロとしての在り方」を叩き込んでくれる講師に出会えたからです。
もし今の環境で伸び悩みを感じているなら、学ぶ環境そのものを見直すのも一つの戦略です。
私が一発合格するために選んだ「実技に強い講座」の選び方を公開しています。
▶ 【一発合格者が厳選】実技で苦労したくない人のための養成講座選び
こちらも是非参考にしてください!
私が練習相手も承ります!
また、ここまで「質問力」の磨き方をお伝えしましたが、質問力は「頭で覚える」ものではなく「口で覚える」ものです。
ぶっつけ本番で頭が真っ白にならないためには、「初対面の相手」と「本番形式」で練習する経験が不可欠です。
もし周りに練習相手がいない、あるいは「もっとリアルな若手役で練習したい」という方のためにココナラサービスを始めました。
私が練習相手を務めさせていただきますので、お気軽にご相談ください!
↓画像をクリック!
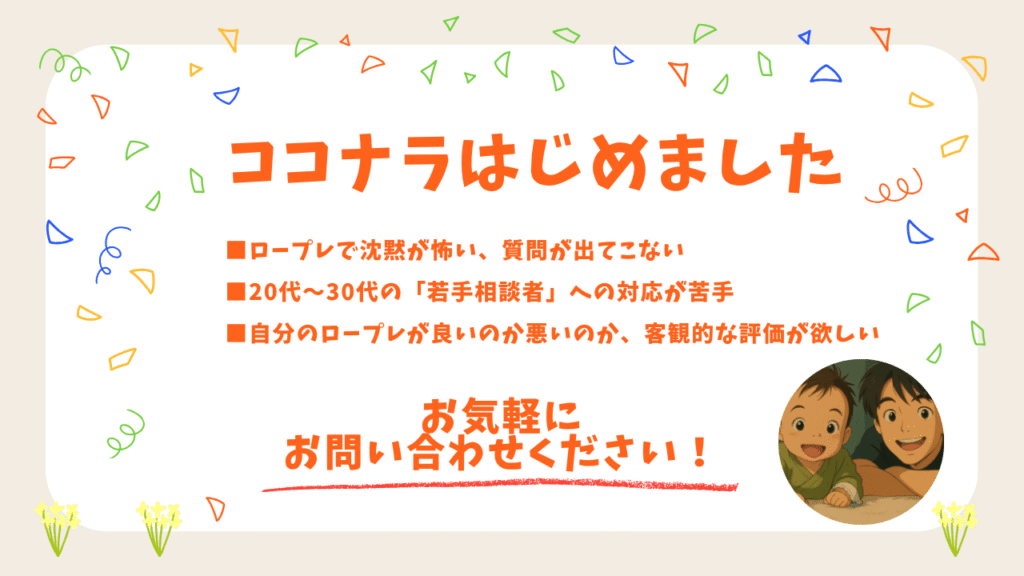
あなたの合格を全力応援しています!!
▶ 【実技試験・口頭試問】評価を上げる!キャリアコンサルタント「視点」の磨き方
▶ キャリアコンサルタント資格取得後の仕事と収入源を詳しく見る!
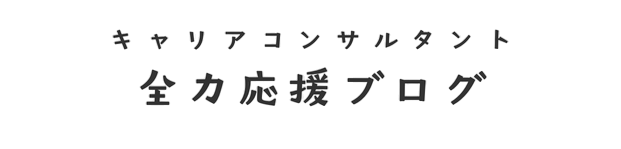





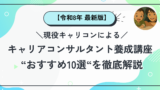



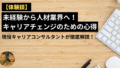
コメント